2024/05/23
弁護士の守秘義務はどこまで?範囲や違反・解除されるケースを徹底解説

この記事では、弁護士の守秘義務について解説します。
弁護士は法律で秘密保持の権利と義務が定められています。しかし、守秘義務に該当する範囲は多岐にわたり、どのような情報が違反になるか明確に判断しにくい場面も少なくありません。
この記事では、弁護士の守秘義務の範囲を事例別に解説します。違反した場合に課されるペナルティや正当な理由として解除されるケースもお伝えするので、弁護士の守秘義務に関して理解を深めたいという方は、この記事を参考にしてください。
- 弁護士の守秘義務とは
- 【事例別】弁護士の守秘義務の範囲
- 弁護士が守秘義務に違反したらどうなるか
- 弁護士の守秘義務が正当な理由で解除されるケース
弁護士・法律事務所が顧客から選ばれ続けるためには、機密性の高い顧客情報や訴訟資料の保護が不可欠です。情報漏洩が発生すれば、法的責任や事務所の信用失墜につながるリスクがあります。
株式会社レアラが提供する「LEALA」は、世界最高水準のセキュリティ性を誇る顧客案件管理システム”Salesforce”を開発基盤にした法律事務所特化型のシステムです。
顧客・案件管理をはじめ、タイムチャージや請求管理、工数や売上情報の可視化など、幅広い法律事務所業務に対応。データ保護を強化することで、弁護士が安心して業務に専念できる環境を提供します。
導入事務所様からは、「セキュリティ 、データベース、 仕組みの3点において、非常によくできているシステム」と高評価をいただいています。
下記の画像から資料請求でき、無料個別相談では貴所の業務に最適な具体的活用方法をご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士の守秘義務とは?
弁護士の守秘義務は、『弁護士法』 23条で以下のように定められています。
(秘密保持の権利及び義務)
弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
※引用:弁護士法 23条丨e-GOV法令検索
つまり、弁護士が仕事を通して得た情報を無断で漏らしたり利用したりしてはいけないといった法律です。また、『弁護士職務基本規程』にも同様の規定があります。
第23条(秘密の保持)
弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない
※引用:弁護士職務基本規程丨日本弁護士連合会
弁護士の守秘義務は、依頼者が安心して情報を開示できる環境を保障するために、法律や規程によって定められている弁護士の重要な役割です。守秘義務があるおかげで、弁護士は依頼者の利益のために法律サービスを提供できるといえるでしょう。
【事例別】弁護士の守秘義務の範囲
ここでは、事例別に弁護士の守秘義務の範囲を解説します。
守秘義務に該当する情報は、”職務上知り得た秘密”に当たるものです。自分が把握している情報が守秘義務の範囲であるかを判断する際には、弁護士の仕事を通じて得た秘密であるかどうかを考えましょう。ここでは、下記4点について解説します。
- 依頼者が自ら話した情報
- 依頼者が弁護士を解任した事実
- 依頼者ではない相手方の情報
- 職務上ではない第三者から知り得た情報
この記事では、法律事務所(弁護士)の顧客管理について解説していきます。 顧客管理とは、顧客の基本情報や事案の進行状況、重要な通信記録、会計情報などを体系的に管理することです。顧客情報を適切に管理することで、必要な情報にアクセスしやすくなっ[…]
依頼者が自ら話した情報
担当している事件とは直接関係がない事項であっても、依頼者が自分から話した情報は一部守秘義務の対象になるケースがあります。
とはいえ、必ずしも話した内容がすべて守秘義務になるわけではなく、依頼者本人が納得した場合は開示することも可能です。なかには、情報を開示したほうが依頼者にとって有益となる場合もあるでしょう。
依頼者は、担当弁護士が自分の利益のために最大限の法律サービスを提供してくれると信じているため、さまざまな情報を提供します。
大切なことは、依頼者の相談内容や具体的な要望をしっかりとキャッチし、開示すべき情報の範囲を明確にすることです。
依頼者が弁護士を解任した事実
依頼者が担当弁護士を解任した場合、解任の事実も守秘義務の秘密に該当します。
弁護士の解任は、依頼者と弁護士の委任契約に関わる事実です。過去には、弁護士が依頼者の紹介人に”解任された旨”を伝えて精算や書類返還に関する協力を仰いだ結果、弁護士の賠償責任が認められた事例(※)が発生しました。
依頼者と紹介者は同一視してしまう傾向がありますが、まったくの別人であることを念頭に置きましょう。たとえ依頼者と弁護士を仲介した人物であっても、依頼者の了承がない限り解任の事実を伝えてはいけません。
※参考:【不慣れな弁護士のミス→賠償責任|守秘義務違反・情報漏洩編】 | 弁護士業務の限界・職務基本規程|東京・埼玉の理系弁護士
依頼者ではない相手方の情報
先述した弁護士法では、守秘義務の範囲が依頼者に関するものに限定されているかどうかは解釈上考え方がわかれており明らかではありません。”職務上知り得た秘密”と述べられており、依頼者ではなくても仕事を通じて得た情報を漏らすことは禁止されているという解釈もあります。
守秘義務の範囲に関しては、以下の3つの考え方があります。
- 限定説:依頼者の秘密に限られるという考え方
- 非限定説:依頼者の相手方の秘密も該当するという考え方
- 折衷説:依頼者のほかには、依頼者に準ずる者の秘密も該当するという考え方
弁護士のなかでも依頼者の相手方の情報を守秘義務に含むかに関しては見解が異なりますが、相手方の情報も守る必要があると考えておくほうが無難でしょう。
職務上ではない第三者から知り得た情報
職務に関係がない個人的な関係や出会いで知り合った第三者からの情報は、基本的には守秘義務の対象外となります。しかし、その情報が職務に密接に関連している場合や相談内容が法律に深く関わるものであった場合、それは守秘義務に該当します。
例えば、友人から法律に関する相談を受けた場合、依頼者ではなく友人として相談に乗ったとしても弁護士という仕事を理由に相談されたと考えられるため、相談に関する情報は守秘義務の対象です。
金額が発生しない無料相談の場合で得た情報も守る義務があるので、個人的な友人からの相談も守秘義務に当たると考えましょう。
弁護士が守秘義務に違反したらどうなるのか


ここでは、弁護士が守秘義務に違反した場合に課せられる罰則やペナルティを解説します。
下記3点を順番に見ていきましょう。
- 刑法上の罰則
- 民事上のペナルティ
- 懲戒処分
刑法上の罰則
弁護士が職務上知り得た秘密を外部に漏らした場合、刑法134条によって以下のような罰則を受けます。
(秘密漏示)第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
※引用:医薬品販売業者に係る刑法の秘密漏示罪について丨厚生労働省
医療の場で言及されることが多い法律ですが、弁護士や弁護人も刑罰の対象となります。法律によって、懲役や罰金の処罰を受ける場合があることを把握しておきましょう。
民事上のペナルティ
弁護士の守秘義務に関する法律には、民法644条も挙げられます。定められている条文は以下のとおりです。
(受任者の注意義務)第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
※引用:民法644条丨e-GOV
受任された弁護士が、守秘義務を破り依頼人が本来被るはずだった利益を損失した場合、依頼人が弁護士を解任するおそれや損害賠償を請求されるおそれがあります。
また、依頼人と弁護人の間で秘密保持契約を結んだ際には、その条項に基づいたペナルティが別途課されるでしょう。弁護士としての信頼を損ねることになるため、依頼人の情報は慎重に取り扱う必要があります。
懲戒処分
『弁護士法』では、弁護士の懲戒に関して以下のように定められています。
(懲戒事由及び懲戒権者)第56条
弁護士及び弁護士法人は、この法律(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
※引用:弁護士法丨e-GOV
守秘義務違反は先述した弁護士法 23条や弁護士職務基本規程 第23条に違反する行為であり、上記の”品格を失うべき非行”に該当すると考えられます。この場合、以下のような懲戒を受けることになります。
- 戒告
- 2年以内の業務の停止
- 退会命令
- 除名処分
除名処分を受けると3年間弁護士資格を取得できなくなり、他の懲戒を受けた場合でも処分について公表されるため、社会的信頼を失ってしまいます。最悪の場合、弁護士の活動を再開できないケースが考えられるため、守秘義務は遵守する必要があります。
弁護士の守秘義務が正当な理由で解除されるケース
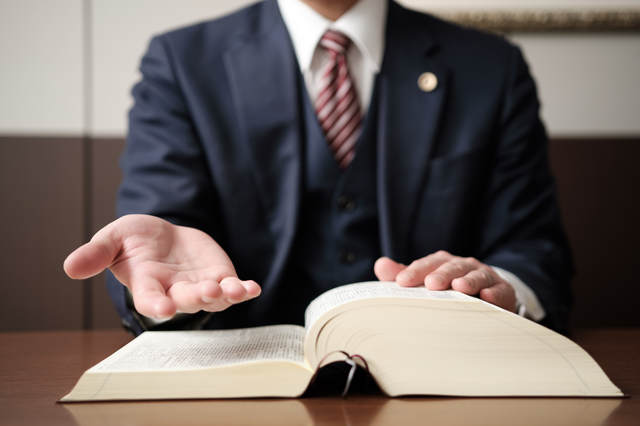
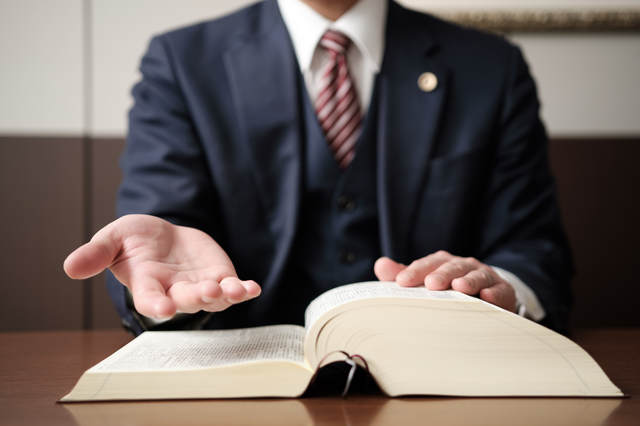
ここでは、弁護士の守秘義務が解除されるケースを具体的にお伝えします。
ここまで解説したように、弁護士の守秘義務は厳しく定められていますが、以下3つのようなケースでは正当な理由として義務が解除されることがあります。順番にチェックしましょう。
- 何らかの目的のため依頼者が同意しているケース
- 税務調査・犯罪調査に協力するケース
- 法律に特別な定めがあるケース
何らかの目的のため依頼者が同意しているケース
依頼者が自らの利益や特定の目的達成のために、弁護士に対して秘密情報の開示を許可するケースがあります。
例えば、弁護士の知り合いの専門家に依頼者の情報を伝えて協力を仰いだほうが、裁判で有利な判決を得られると判断した場合です。通常、依頼者の情報を外部の第三者に漏らすことは禁止されていますが、依頼者本人が自らの利益のために効果的だと判断した場合は守秘義務が解除されます。
この際、依頼者の明確な同意が必要であり、開示の必要性や方法については依頼者に対して十分な説明が必要です。
税務調査・犯罪捜査に協力するケース
受任事件に関して弁護士自身が刑事・民事上の係争の当事者になった場合、弁護士は自己の主張や立証のために事件に関する情報開示が許可されるケースがあります。
また、依頼者や受任事件を通して知り得た情報が税務調査に有効だと判断される場合も、情報開示を認められる可能性があります。
これに対し、犯罪捜査を目的とする場合には、拒否できるケースが一般的です。
法律に特別な定めがあるケース
弁護士の守秘義務が定められている『弁護士法 第23条』では、”但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。”という条文があります。ここで指摘されている別段の定めには、以下のような法律が挙げられます。
【民事訴訟法第197条】
1:次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
(前略)
医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
(中略)
2:前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
※引用:民事訴訟法丨e-GOV
【刑事訴訟法第105条】
(前略)業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
※引用:刑事訴訟法丨e-GOV
【刑事訴訟法149条】
(前略)業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
※引用:刑事訴訟法丨e-GOV
上記3つの法律が根拠となります。自身の状況と慎重に照らし合わせて考えましょう。
弁護士が守秘義務を正しく守るためには情報管理が重要
多くの依頼者を担当する弁護士が守秘義務を正しく守るためには、堅牢なセキュリティ環境の元、情報をしっかりと管理して外部への漏れを防止することが重要です。
情報漏洩の原因には、誤送付や紛失、事務処理・作業ミスが挙げられます。特に、誤送付にはメールの誤送信や書類の封入ミスが該当し、情報漏洩のなかで最も多い原因とされています。
万が一、情報管理に不備があり依頼者の情報が外部に漏れてしまった場合は守秘義務違反となり、先述したペナルティを受けるおそれがあります。また、懲戒処分を受ける場合は弁護士資格を剥奪されたり処分について公開されたりすることがあり、弁護士としての信頼低下に繋がります。
守秘義務を遵守して弁護士としての活動に支障をきたさないためにも、情報管理を徹底しましょう。
情報を一元化するならLEALA(レアラ)のクラウド業務管理システムがおすすめ
一元した情報を安全に管理するなら、法律事務所向けのクラウド業務管理システムLEALA(レアラ)がおすすめです。
LEALAは、数百名規模から数名規模の法律事務所まで幅広くご採用いただいている、弁護士業務を効率化する業務管理システムです。分野や規模問わず全国様々な法律事務所に導入いただいており、実務のフローに沿った機能開発に現役弁護士が携わっています。
世界各国の政府系機関や大手金融機関等も利用している世界最高峰のセキュリティを提供している”Salesforce”をシステム基盤に採用しているので、事務所の資産である情報を安心して管理することができます。
気密性や保全性、可用性、監査性の4つの特性において高い質を維持しており、いずれも高評価を得ているので、大量のデータ管理が必要となる弁護士にはぴったりなシステムだといえます。
この記事では、法律事務所にサイバーセキュリティ対策が必要かどうかを解説します。 法務省の『令和4年版 犯罪白書』によると、サイバー犯罪の検挙件数は年々増加しており、令和3年には12,209件発生しています。多くのクライアントの個人情報を取[…]
案件ごとに依頼者情報やメール・通話などの活動記録、ファイルや会計情報などが自動的に紐付けられるため、入力・確認負担を軽減して作業ミスを防止します。
さらに、案件情報に紐づけてチャットでコミュニケーションができるため、情報が分散せずに所内全体での確認作業が容易となり、誤送付などのミスを未然に防ぐことができるでしょう。
堅牢なセキュリティシステム基盤で法律事務所業務を一元管理したい先生方は、以下のページからLEALA(レアラ)に関する情報が入手できるので、ぜひチェックしてみてください。
弁護士の守秘義務に関するよくある質問
ここでは、弁護士の守秘義務に関するよくある質問に回答します。
下記3つの質問について1つずつ見ていきましょう。
- 弁護士の事務員にも守秘義務はある?
- 弁護士による守秘義務違反の具体的な事例は?
- 弁護士の守秘義務は電話の無料相談も該当する?
弁護士の事務員にも守秘義務はある?
弁護士事務所で働く事務員に対しては、法律などで守秘義務は課されていません。
しかし、事務員は弁護士の仕事の一部を担い補助する役割にある以上、依頼人に関する情報は守る必要があります。実際に、『弁護士職務基本規定』の第十九条では以下の通り定められています。
【事務職員等の指導監督】
第十九条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。
※引用:弁護士職務基本規定(第十九条)|日本弁護士連合会
万が一、事務員が情報漏洩をしてしまった場合、事務員を雇用する弁護士が懲戒処分を受けることになります。そのため、事務員は事務所で知り得た情報をむやみに他人に話すべきではありません。
また、雇用主である弁護士は事務員の教育を徹底することが大切です。
弁護士による守秘義務違反の具体的な事例は?
過去には、原告が被告である弁護士に対して慰謝料150万円を請求した事例があります。事件の概要は以下の通りです。
<事件の概要>
1, 原告女性は職場で受けたセクハラについて弁護士A・Bに相談していたが、慰謝料に関して弁護士Bと見解の違いがあった。
2, 原告はインターネット上でS弁護士会に所属する被告弁護士に対して、受けたセクハラの内容や弁護士Bとの見解の違いを記載したメールを送付した。
3, 被告弁護士が集会などでメールの内容を話し、弁護士A・Bは原告が弁護士達の実名を挙げて話していることを原告に対して叱責した。
4, 原告は被告にメールのことを弁護士Bに話したか尋ね、被告弁護士は守秘義務違反に当たらないとしたが、原告は被告の違反によって精神的苦痛を受けたとして慰謝料150万円を請求した。
※引用:弁護士守秘義務違反事件丨一般社団法人 女性労働協会
上記の事例では、弁護士が職務ではなくインターネットを通じて得た情報を弁護士仲間に漏洩したことで、慰謝料を請求されています。
実際に150万円の支払い請求は認められなかったものの、弁護士法第23条に反するとみなされ、被告弁護士に対して20万円以上の支払いが判決として下されました。
弁護士の守秘義務は電話の無料相談も該当する?
金額の発生有無に関係なく、弁護士が依頼者について知り得た情報には一部守秘義務があります。そのため、料金を得ずに実施した電話の無料相談であっても、そこで得た情報は漏洩せずに守らなければいけません。
弁護士の守秘義務は社会的信頼に影響するケースがある点に注意しよう
この記事では、弁護士の守秘義務について解説しました。
弁護士の守秘義務は、依頼者が法律サービスによって利益を得るために安心して情報を開示できる環境を作ることを目的とし、『弁護士法』や『弁護士職務基本規程』によって定められています。
違反すると罰則やペナルティーを受けて社会的信頼を失い、最悪の場合弁護士としての活動を続けることが困難になるでしょう。守秘義務の範囲や解除になるケースなどの留意点を念頭に置き、顧客からの信用を失墜させる行為を未然に防ぐことが重要です。
また、システムを用いて個人情報を取り扱う場合には、堅牢なセキュリティの基で情報管理を行うことが必要です。この記事で紹介したクラウド業務管理システムLEALA(レアラ)は、世界最高峰のセキュリティを提供しているSalesforceをシステム基盤に採用しているため、大切な情報を安心して管理することができます。書類の誤送信や紛失による情報漏洩などを防止し、弁護士事務所の業務効率化もサポートします。
気になる方は、ぜひ一度チェックしてみてください。







