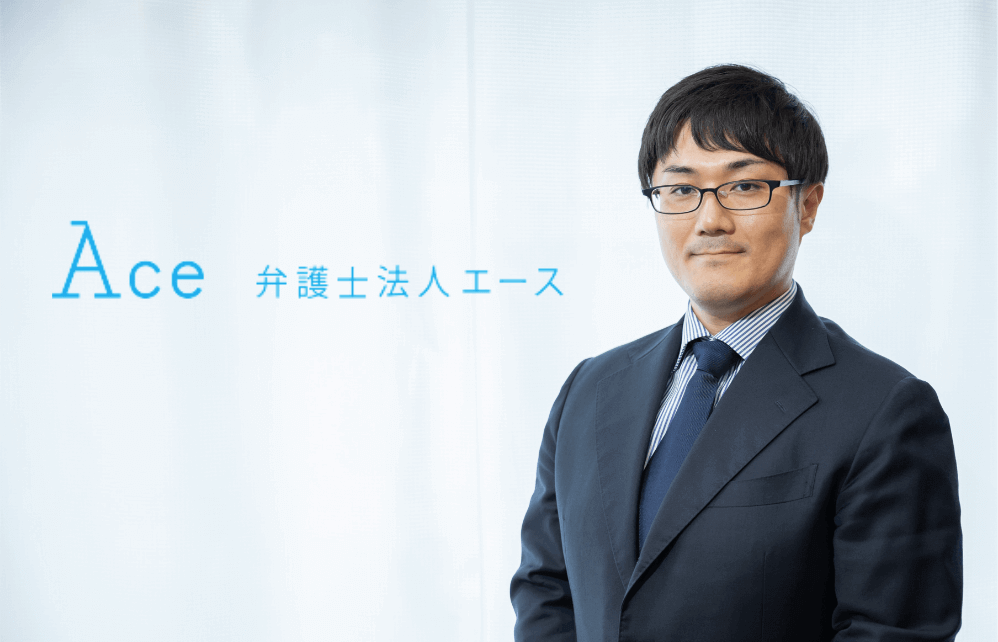経営判断の材料になる実感
LEALAを導入したことで、顧問業務の実働時間や作業量を可視化できるようになった。それは単なる便利なツールというだけでなく、日々の判断や将来の方針決定に影響を与える基盤としての意味を持ちはじめている。
京谷先生:「例えば、どのような業務にどのくらい時間をかけ、

紹介チャネルと売上・件数の可視化が可能に
事務所の収益構造を分析するうえで、どのチャネルから案件が流入しているか、紹介先ごとの売上や件数はどうなっているかといった情報も欠かせない。こうしたデータは、事務所の戦略設計にもつながっているという。
京谷先生:「紹介チャネルごとの可視化は、LEALAを入れてから本格的に取り組むようになったテーマです。これまでは、非常に感覚的なところだったのですが、
弁護士ごとの業務量と案件進捗の見える化
案件の進捗状況や、弁護士ごとの抱えている件数についても、LEALAによって把握しやすくなった。特に、進行中・終了処理待ち・放置状態などのステータス分けができる点は、事務所全体のリスク管理にも寄与している。こうした数値や可視化されたデータは、経営会議の資料にも反映されるようになってきているという。
京谷先生:「うちでは、委任前・進行中・終結済みだけど事務処理が終わっていない…といったフェーズに分けて案件を管理しているんです。LEALAではそれが一覧で、しかもグラフで見えるので、“誰がどのフェーズの案件を何件持っているか”が一目で分かります。以前は頭の中に頼っていた部分が大きかったですが、今は可視化されたリストとして見えるので、放置リスクのある案件にも気づきやすくなりました。」
KPI管理の可能性と運用上の課題
KPI的な視点での業務分析も行いたいが、現時点でLEALA上での運用は実現していない。とはいえ、弁護士法人として複数名・複数拠点を持つ事務所において、KPI管理の仕組みを構築していくことは避けては通れないテーマだと感じているという。
京谷先生:「KPI的な指標は、Excelで管理しています。本当はLEALA上でそのまま出せれば理想なんですけど、現状そこまで運用に落とし込めてはいないですね。技術的には可能だと思うんですけど、どういう指標を見たいかがはっきりしていないと設計が難しい。あとはやっぱり、定着させるには時間も人手も必要なんですよね。」
情報を蓄積するところから活用する段階へ
LEALAの導入により、業務の効率化・可視化が進み、職員間の情報共有もスムーズになってきた。情報入力を事務局がやるものとするのではなく、弁護士も含めて全員が使う状態を作っていくことが重要だと考えている。一方で、情報資産を活用したり、使用していない機能を活用することは今後の課題として残っている。
京谷先生:「日々入力している情報を、経営判断や業務改善にどう活かしていくかですね。誰かだけが使っても意味がないので、情報を入れたら便利になるという実感を事務所全体で持てるようにしていきたいです。また、他の事務所さんがどういう工夫をしているのか、もっと知れたら参考になります。たとえば分野別カルテの活用例とか、KPIの設計例とか。そういう使い方の提案があれば、次の一歩が踏み出せるんじゃないかと思います。」
※記載の内容は、2024年11月時点のものです。